私たちは前回の記事までで、『存在と時間』読解の前半戦を戦い終えた。今回の記事では読解全体のプランについて一点補足しつつ、これまでの歩みを振り返っておくこととしたい。
今回の読解では第44節までを前半戦、それより後を後半戦としている論ずるという体裁をとっている。
7月29日から9月1日にかけて論じた真理論の部分(これは『存在と時間』でいうと、前半と後半の区切りとなる第44節にあたる箇所を論じたものである)はいわば、前半戦のまとめというかクライマックスに当たるとも言えるわけで、この真理論をもって、これまでの議論にはいったんの結論がもたらされた。すなわち、「現存在は真理のうちで存在している」。現存在であるところの人間は、「覆いをとって発見する」という存在のしかたを有する比類のない存在者として、世界への開かれのうちに立つのである(これが、真理論の観点から見られた際に「世界内存在」という術語が有する意味である)。
ただし、これまでの読解においては、本来は第44節よりも前に出てくるはずの〈ひと〉論、そして、この語と密接に結びついた「世界への頽落」という語には触れられていない。
これは言うなれば、叙述の意図の違いによるものである。ハイデッガーは、「日常性における現存在という主題に関する総括であるところの第44節にたどり着くまでに、日常性に関する議論はすべて済ませておく」という意図から、〈ひと〉と頽落については、それよりも前に論じるという道をとった。これだと、内容上のまとまりはよいのだが、『存在と時間』の思考のうねりを理解し、経験する(そして、この本の中のさまざまな概念が、どのような問題意識のもとで生み出されていったのかを追体験する)という点から見ると、若干流れがわかりにくくなる。
要するに、『存在と時間』の叙述のスタイルは「議論を分かっている人間の目から見ると確かにそうなる理由もわかるのだが、プレゼンテーションの順番としてはおそらく、最高のものになっているとは言えない」のである。したがって、今回の読解では、最初から最後までそのまま読み進めてゆくうえで、『存在と時間』の議論の内容に最も入ってゆきやすいと思われる順序で読み進めてゆくこととした。原著とは順番が違ってしまうが、一応、その点を補足させていただいた次第である。
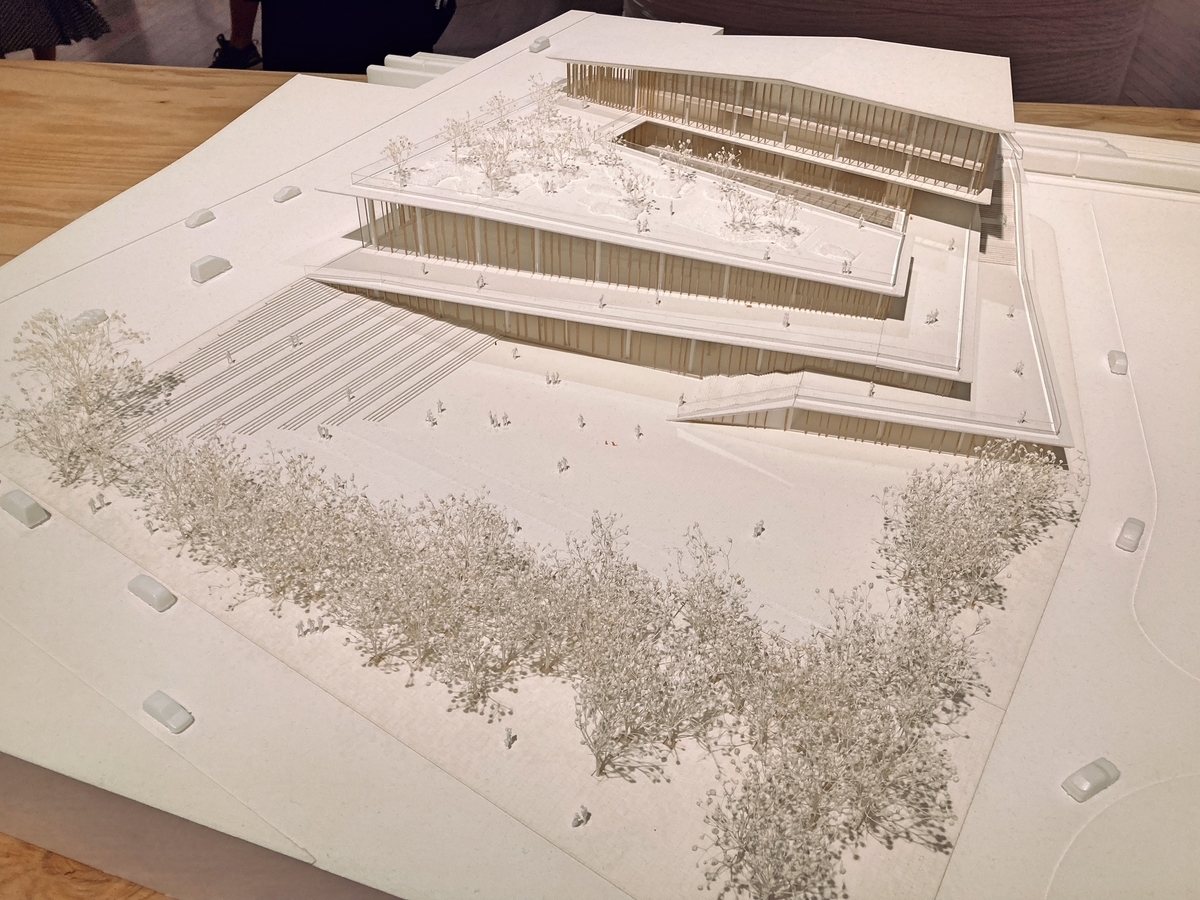
さて、ここまでの四ヶ月間で『存在と時間』を読み直しつつあらためて実感されたのは何よりも、この本の持つ今日的な重要性ということに尽きる。
ハイデッガーが残した思索の影響力は甚大である。具体的に言うならば、エマニュエル・レヴィナスやジャック・ラカン、ジル・ドゥルーズ、そして、1995年から2014年にかけて行われた「ホモ・サケル」プロジェクトで政治哲学の分野に多大な貢献をなしたジョルジョ・アガンベンなど、ハイデッガーよりも後に活躍した本質的な哲学者・思索者たちはみな、まさしくたった一人の例外もなく(!)、彼の思索を極めて強く意識しながら自らの仕事を行なっていた。「どのようなスタンスを取るかは別にするにしても、ハイデッガーと向き合うことなくしては、話が始まらない」という状況は、少なくとも2014年までは続いていたわけである。2021年の現在においても、これとそれほど違った状況にあるとは思われない。
そういうわけで、私たちは今や次のように言ったとしても、それほど誇張にはならないであろう。すなわち、20世紀を代表する哲学者であるマルティン・ハイデッガーの仕事は今日でもなお、アクチュアルな問題提起としてしっかりと読み、受けとめ、継承し、場合によっては対決すべき必須文献であり続けている。かつて、カントの批判哲学がそうであったのと同じような意味で、ハイデッガーの「存在の思索」は21世紀の哲学者たちにとって、避けることのできない参照項であり続けているのである。その意味で、1927年に出版された『存在と時間』を「いま話題の本」として精読することの必然性をあらためて確認しつつ、私たちとしては、次回の記事から読解の後半戦に取りかかることとしたい。