論点:
他者の真理についての問いは、他者との別離あるいは喪失の経験を通して、その切実さを増してゆく。
「わたしはあなたについて、何を知っていたのだろう。」このような問いが痛みとともに切実さを帯びてくるのは、多くの場合、わたしがあなたを失った後のことである。
真理の問いはいつでも、遅れて立てられる。わたしはあなたについて、何を知っておくべきだったのだろう。あなたがわたしから去ってしまうことがないようにするためには、何が必要だったのだろうか。
出会いと別れにはたいていの場合、容易には動かしがたい必然性が伴っていて、あれほど多くの時間を過ごしたわたしとあの人との関係が、お互いの人生を先に進んでゆくためにも解消されなければならなかったということもしばしばである。新しいものが始まるためには身を切るような痛みが必要であるというのが、おそらくは、私たちの生きているこの世界を動かしている法則なのだろう。
しかし、それにも関わらず、ひとは「私たちには何が必要だったのだろう」と問いを立てることを、やめることができない。わたしとあなたが実存することの真理をめぐって、問いを立て続けること。もしもあなたに対する真摯さなるものが存在するとするならば、それは一つには、答えが出るかどうかには関わることなく、あなたについての問いを問い続けることのうちにあると言えるのではないだろうか。
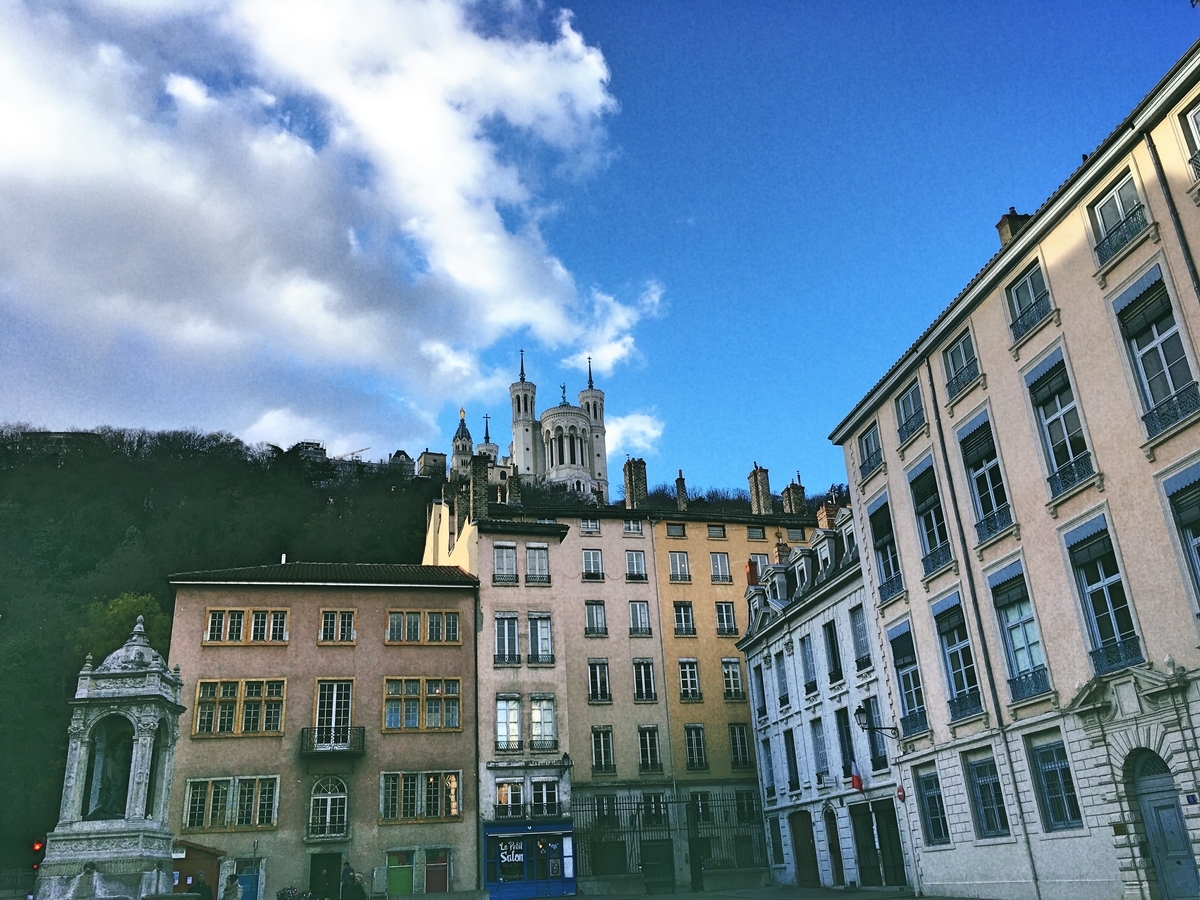
本を読んでいて、また、誰かと会話していて、わたしは、今まではっきりと気づいていなかった何らかの事実に気づく。すると、わたしの思考はわたしのもとを去っていったあの人のところへ向かっていって、関係が壊れてしまったその時期をもう一度、別のしかたで繰り返そうとする。
もしかすると、このことを知っていたら、わたしがあなたを失うこともなかったのではないか。知っていたのなら、わたしはあなたにあんなことを言わなくてすんだのに。この意味からすると、ひとが哲学や文学の本を繙くのは、決定的な仕方で失ってしまった他者との関係を、その他者と直接に関わるのとは別のしかたで継続するためなのではないかとも思えてくる。悲歌(エレジー)というのは文学の本質をその中核において捉えた言葉なのであって、ものを書く営みは、あなたを失うという出来事によって生み出された空虚のうちで発される叫びとともにしか始まらないものなのかもしれない。
哲学もまた他者をめぐって、他者の真理とは何かという問いを立てる。哲学である以上、その問いはあらゆる情念のくびきから解き放たれた、透明なものでなければならないけれども、その問いはおそらく、問う人間が経験した数多くの別れがもたらした痛みとともに、初めて切実な問いとなることだろう。哲学は痛みを痛みとして歌うかわりに、痛みの真理を問うのでなければならない。