論点:
世界はわたしが生まれていなかった時にも存在したし、わたしが死んだ後にも続いてゆくであろう。
たとえば、筆者が哲学者として考えていることも、二十一世紀を生きている哲学者であるということから規定を受けているに違いない。人間として生きるということは、歴史的に生きることである。未来の人間から見るならば、私たちを形作っている時代性は私たち自身にとってよりも、ずっと明確になっていることだろう。
わたしがものを感じ、考え、話すよりも前に、無数の人間たちがすでに感じ、考え、語り続けてきたのである。そして、わたしが死んだ後にも同じ営みはなされ続けるであろうし、その中の幾らかの人々は、哲学に身を捧げることだろう。
わたしはこうした途方もない広がりを持った過去と未来に挟まれて、一人の人間としての生を生きる。わたしは、全てを見渡すことのできる全能者の眼ではないのであって、いずれ必ず滅びてゆく肉体をまとった一人の人間として、この一度限りの「わたしはある」を最後まで生き抜かなければならないのである。
世界といっても、そう呼ぶことができるような何か一つの実体的なものがあるわけではないけれども、存在者から存在者へとつながってゆく限りない連関とその総体として、世界は厳として存在している。そして、この世界の存在は生まれ、かつ死んでゆくわたしの存在を超絶するような仕方で続いてきたし、これからも続いてゆくであろうことは決して動かないように思われるのである。
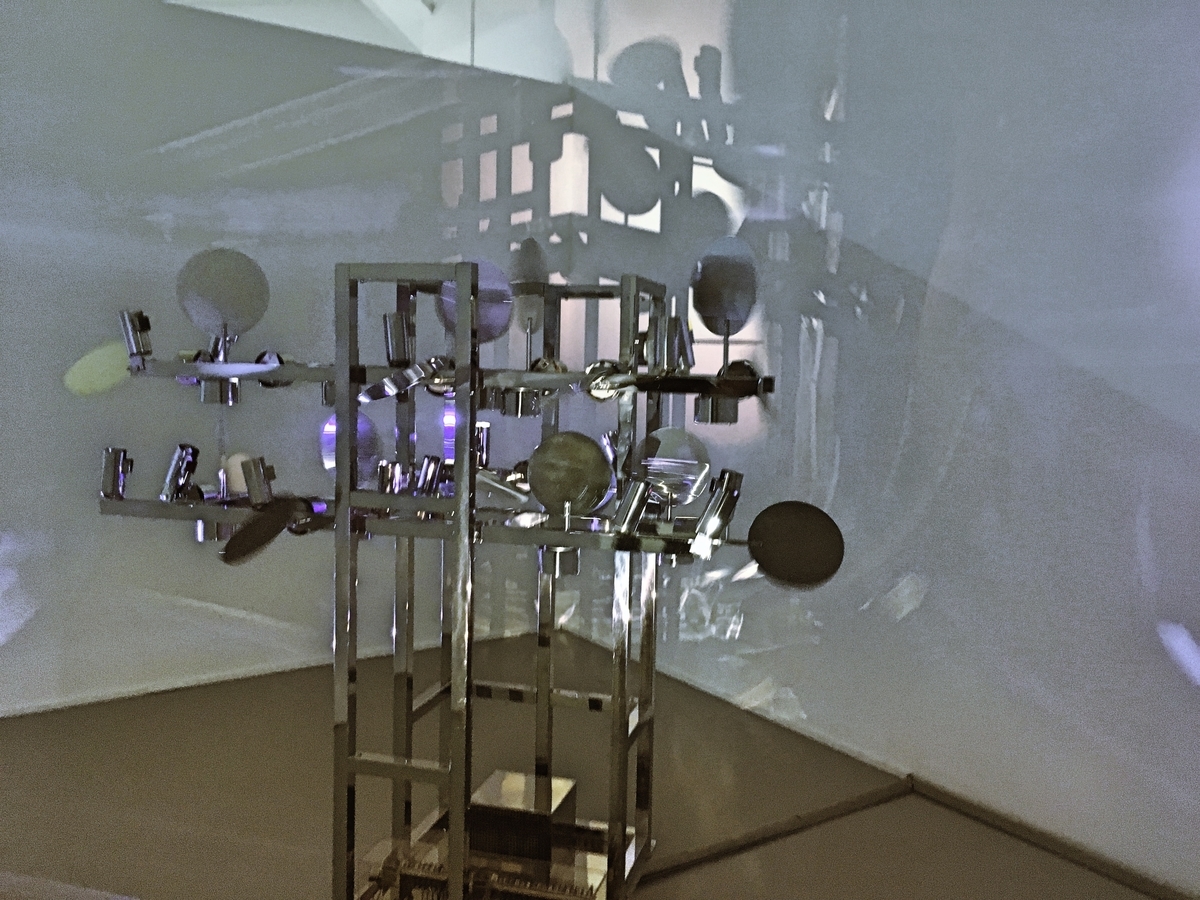
たとえば、風の音によって驚かされて秋の訪れを知るとき、働きかけているのはわたしではなくて、世界の方である。
身体に風が吹くのを感じ、音を聞くのはわたしである。風の現れによってわたしは風の存在を知り、秋が訪れていることを知る。しかし、大気と天体とが秋の訪れという出来事を生起させているのでなかったならば、わたしがそのことを知るということもどうして起こりえただろうか。
「ある」は、「現れる」を超えているのではないか。一世紀前に行われた現象学の探求は、現れることの比類のなさを明らかにした。その探求によって哲学は、知ることと現れることの間の切り離しがたい結びつきを、その等根源性を知ったけれども、果たしてその探求は、「ある」ということの深さを測ることができるものだったのだろうか。あるいは、「ある」ことの深さは、そもそも人間によって測り尽くすことができる類のものなのだろうか。「ある」を「存在の超絶」として、現象学の彼方で考えてみる必要があるのではないかと筆者が考えているゆえんである。私たちは、「ある」という言葉が指し示している根源的な事象の領域を、一歩一歩、慎重に踏みしめるようにして進んで行かなければならない。